2025年04月16日
観劇 『屋根の上のバイオリン弾き』
観劇 『屋根の上のバイオリン弾き』 愛知県芸術劇場(名古屋栄にあります)
原題:Fiddler on the Roof (Fiddlerは、ラテン語でバイオリン弾きです)
ラテン語:イタリア半島中西部で生まれた言語で古代ローマの拡大とともにヨーロッパに広まった。西ローマ帝国が476年滅亡。東ローマ帝国が1453年滅亡
台本:ジョセフ・スタイン 時代は1905年(日本では明治38年。日露戦争で日本が勝利したときです) 劇中の場所は、『アナテフカ』というところで、観劇していて、現在のウクライナのどこかに思えました。
俳優:
テヴィエ(市村正親 いちむら・まさちか。5人娘のおやじさん。帝政ロシア領に住むユダヤ人で牛乳屋を営んでいる)
ゴールデ(鳳蘭 おおとり・らん。テヴィエの妻)
ツァイテル(長女 美弥るりか みや・るりか)
モーテル・カムゾイル(ツァイテルの彼氏 上口耕平 うえぐち・こうへい)
ホーデル(次女 唯ふうか ゆづき・ふうか)
パーチック(ホーデルの彼氏 内藤大希 ないとう・たいき)
チャヴァ(三女 大森未来衣 おおもり・みらい)
フョートカ(三女の彼氏 神田恭平 かんだ・きょうへい)
さらに、四女シュプリンツェ(宮島里奈)、五女ビルケ(東菊乃)がいますが、外見が高校生か中学生ぐらいの女優さんに見えました。劇中、当人たちの恋愛話はありませんでした。
ラザール・ウォルフ(肉屋。お金持ち。今井清隆)
屋根の上のバイオリン弾きの意味:冒頭付近でテヴィエ(市村正親さん)から説明があります。屋根の上で不安定な体勢でバイオリンを弾くことと、ユダヤ人の不安定な暮らしぶりを重ねてあります。
バイオリン弾き役の俳優さんは、劇中、たいてい、屋根の上でバイオリンを弾いていますが、劇中の会話には入ってきません。観ていて、バイオリン弾きは、『妖精』のようなものだと感じました。
現在の社会情勢として、ウクライナとロシアが戦争状態で、イスラエルのユダヤ人がパレスチナガザ地区のパレスチナ人を攻撃していて、劇中の会話の中に、現在のウクライナの首都、『キーウ』という地名も出てきて、観るほうはちょっと複雑な気持ちになります。
されど、意識を変えてみると、わたしたち世代のもうひとつ上の日本人世代と似通った(にかよった)状況があることに気づきます。物語の素材は、結婚の話です。
劇中では、長女、次女、三女の結婚話で、すったもんだの大騒ぎがあるのですが、わたしの親や叔父・伯母の世代が体験した結婚話の状態と内容が同じです。
今でこそ、結婚は両性の合意で成立しますが、昔は、個人+個人ではなく、家+家でした。見合い結婚が多かった。跡取り目的で、養子の話も多かった。
わたしがこどもの頃は、女性の側から見て、『恋愛と結婚は違う』という言葉をよく聞きました。『一番好きな人とは結婚できないけれど、二番目に好きな人なら結婚できるときもある』という言葉も聞いたことがあります。要は、男性に資力(財力)があればいいのです。
お互いに、異性である相手のことを良く知らないまま、親が決めた相手と結婚していました。そして、どちらかといえば、女性のほうが、離婚はなるべくしないようがまんしていました。
結婚においては、まずは、収入を得て、生活していくことが第一目標でした。そんな時代がありました。基本は男尊女卑の社会が、当時の秩序でした。
こちらの劇中では、娘たちの結婚相手を親たちが段取りするのですが、娘たちは親たちの意向に従わないので、娘たちの結婚をめぐって、すったもんだの争いが起きます。親たちが決めたお金目当ての結婚相手などを、娘たちは拒否するのです。
娘たちの父親である主役のテヴィエは、最初、頑固者(がんこもの)に見えるのですが、娘たちから強く主張されるとたいてい引き下がるのです。テヴィエはいい人です。
とくに今回の観劇に関する写真はありません。
思い出すままに、感想をぽつりぽつりとこれからここに落としてみます。
あらすじを知らないまま観劇しました。
一家の苦労話だろうと予想しながら観始めました。
舞台装置がとてもきれいです。美しい。
ステージに登場してきた人たちは、お人形が動いているようでした。きれいなお人形のような役者さんたちです。
仲人(なこうど)とか、司祭とか、しきたり(伝統)とか、ああ、結婚の話が始まったと思いました。
そして、お金の話です。
肉屋のおやじが、牛乳屋の(主役のテヴィエ、市村正親)長女と結婚する話で始まります。肉屋のおやじの妻は死んでいて、再婚です。長女は何も知りません。長女のいないところで、結婚の約束が成立してしまいました。肉屋のおやじは、長女の親であるテヴィエよりも年上です。それでもかまわないのです。なぜなら、肉屋はお金持ちだからです。男にお金があることが大事なのです。されど、長女は当然反発します。
そんな感じで、次女、三女の結婚話が素材になって、すったもんだの争いが起きる劇です。
お金持ち、貧乏、お金か愛情か、ドラマでは、よくある素材です。
安息日(あんそくび):劇中でよく出てきた言葉です。日曜日のことだろうか。調べました。休息・礼拝のための日。テヴィエたちはユダヤ教なので、金曜日の日没から土曜日の日没だそうです。
舞台を観ていて、『タイミングの良さ』に感心しました。
家のセットがあって、人が家の中にある別の部屋に入っていくと、同時に、家の外から別の人が入ってきます。ものすごくきちんとしたタイミングで驚きました。そのほかのことについても、ピシッピシッと動きがきちんと決まっていて、稽古(けいこ)の成果だと感心しました。
演劇のテーマの根底には、『平和』があると感じました。
全体的に、ロシア人に迫害のような対応を受けているユダヤ人の情景があります。
ユダヤ人にとっての、『人間と神の賛歌』がありました。偉大なものを賞賛(しょうさん。ほめたたえる)のです。
舞台は、ときおり、お祭りのようです。歌があって、ダンスがあって、音楽が鳴り響きます。
すごい!と声が何度か出そうになりました。大迫力です。にぎやかで、観ているこちらも楽しい気分になれました。
結婚相手のことで、娘たちから文句を言われて、板挟みになる父親のテヴィエ(市村正親)ですが、がんこそうに見えても、譲る時は譲るという判断をする、いいおやじさんです。
『約束』にこだわる内容でした。
宗教がかなりからんでくるのですが、あまり気にしないようにして観劇しました。
信仰深い人たちの物語です。
若い役者さんたちの歌声に伸びがあって、聴いていて気持ちがいい。
恋愛の成就について応援したくなります。
テヴィエ(市村正親)の動作や言葉にユーモアがあって大笑いできました。
市村正親さんは、最初なんとなくとっつきにくい人かなあと感じましたが、ときおりのしぐさが、志村けんさんみたいで笑いました。おもしろい。76歳の方ですがお元気です。
なんというか、時代背景として、人の気持ちのよりどころが、神しかない時代です。法律とか、思想とか、道徳とか、そういうものはまだぼんやりしていて、宗教で集団が管理されている時代だと受け取りました。宗教で、集団の、『秩序』が保たれているのです。劇中では、『しきたり(伝統)』と表現されていました。
歌劇は大迫力で、ときに、オペラのようだと思いました。(オペラを観たことはありませんが)
最終的には、ユダヤ人たちは、ロシア人たちに住んでいた土地を追い出されてしまいます。
エルサレムへ行く人もいましたが、大半のユダヤ人は、アメリカ合衆国への移住を目指しました。
最後のあたりで交わされた(かわされた)言葉が、『シャローム』という言葉でした。意味は、『平和』です。
最後は尻すぼみするような雰囲気で静かに幕切れとなってしまってあっけなかった。まあ、そういう終わり方もあるのでしょう。以前名古屋伏見にある御園座(みそのざ)で観た、山崎育三郎さんのミュージカル、『トッツィー』もそんな幕切れでした。
流れていた曲で、第1幕の最後に流れた、『陽は昇り又沈む』は聴いたことがある曲です。いい感じの曲です。
オーケストラのみなさんは、舞台の右奥の部屋(あるいはスペース(区域))におられて、ときおり、その場所が見えるように舞台装置が動きました。それもまた、座席から観ていていい感じでした。
観客は、わたしたちのような年金生活者の夫婦が多かった。年配の男女です。
ラストのカーテンコールでは、2000人ぐらいいた観客が総立ちのようになって、大きな拍手が続いて、何度も幕が上がったり下がったりして、出演者のみなさんがたが、せいぞろいでステージの前の方へ出てきて何度も頭を下げておられました。壮観でした。
幕間休憩中(30分間ぐらい)のトイレが大混雑でした。男性客が意外に多く、男性用トイレも行列でしたが、男はそれなりにスムーズに前へ進んでいました。
女性用は、1階のトイレだけではなくて、2階、3階、4階、5階と上のほうが、たぶん利用者が少なくて、穴場のような気がしました。
原題:Fiddler on the Roof (Fiddlerは、ラテン語でバイオリン弾きです)
ラテン語:イタリア半島中西部で生まれた言語で古代ローマの拡大とともにヨーロッパに広まった。西ローマ帝国が476年滅亡。東ローマ帝国が1453年滅亡
台本:ジョセフ・スタイン 時代は1905年(日本では明治38年。日露戦争で日本が勝利したときです) 劇中の場所は、『アナテフカ』というところで、観劇していて、現在のウクライナのどこかに思えました。
俳優:
テヴィエ(市村正親 いちむら・まさちか。5人娘のおやじさん。帝政ロシア領に住むユダヤ人で牛乳屋を営んでいる)
ゴールデ(鳳蘭 おおとり・らん。テヴィエの妻)
ツァイテル(長女 美弥るりか みや・るりか)
モーテル・カムゾイル(ツァイテルの彼氏 上口耕平 うえぐち・こうへい)
ホーデル(次女 唯ふうか ゆづき・ふうか)
パーチック(ホーデルの彼氏 内藤大希 ないとう・たいき)
チャヴァ(三女 大森未来衣 おおもり・みらい)
フョートカ(三女の彼氏 神田恭平 かんだ・きょうへい)
さらに、四女シュプリンツェ(宮島里奈)、五女ビルケ(東菊乃)がいますが、外見が高校生か中学生ぐらいの女優さんに見えました。劇中、当人たちの恋愛話はありませんでした。
ラザール・ウォルフ(肉屋。お金持ち。今井清隆)
屋根の上のバイオリン弾きの意味:冒頭付近でテヴィエ(市村正親さん)から説明があります。屋根の上で不安定な体勢でバイオリンを弾くことと、ユダヤ人の不安定な暮らしぶりを重ねてあります。
バイオリン弾き役の俳優さんは、劇中、たいてい、屋根の上でバイオリンを弾いていますが、劇中の会話には入ってきません。観ていて、バイオリン弾きは、『妖精』のようなものだと感じました。
現在の社会情勢として、ウクライナとロシアが戦争状態で、イスラエルのユダヤ人がパレスチナガザ地区のパレスチナ人を攻撃していて、劇中の会話の中に、現在のウクライナの首都、『キーウ』という地名も出てきて、観るほうはちょっと複雑な気持ちになります。
されど、意識を変えてみると、わたしたち世代のもうひとつ上の日本人世代と似通った(にかよった)状況があることに気づきます。物語の素材は、結婚の話です。
劇中では、長女、次女、三女の結婚話で、すったもんだの大騒ぎがあるのですが、わたしの親や叔父・伯母の世代が体験した結婚話の状態と内容が同じです。
今でこそ、結婚は両性の合意で成立しますが、昔は、個人+個人ではなく、家+家でした。見合い結婚が多かった。跡取り目的で、養子の話も多かった。
わたしがこどもの頃は、女性の側から見て、『恋愛と結婚は違う』という言葉をよく聞きました。『一番好きな人とは結婚できないけれど、二番目に好きな人なら結婚できるときもある』という言葉も聞いたことがあります。要は、男性に資力(財力)があればいいのです。
お互いに、異性である相手のことを良く知らないまま、親が決めた相手と結婚していました。そして、どちらかといえば、女性のほうが、離婚はなるべくしないようがまんしていました。
結婚においては、まずは、収入を得て、生活していくことが第一目標でした。そんな時代がありました。基本は男尊女卑の社会が、当時の秩序でした。
こちらの劇中では、娘たちの結婚相手を親たちが段取りするのですが、娘たちは親たちの意向に従わないので、娘たちの結婚をめぐって、すったもんだの争いが起きます。親たちが決めたお金目当ての結婚相手などを、娘たちは拒否するのです。
娘たちの父親である主役のテヴィエは、最初、頑固者(がんこもの)に見えるのですが、娘たちから強く主張されるとたいてい引き下がるのです。テヴィエはいい人です。
とくに今回の観劇に関する写真はありません。
思い出すままに、感想をぽつりぽつりとこれからここに落としてみます。
あらすじを知らないまま観劇しました。
一家の苦労話だろうと予想しながら観始めました。
舞台装置がとてもきれいです。美しい。
ステージに登場してきた人たちは、お人形が動いているようでした。きれいなお人形のような役者さんたちです。
仲人(なこうど)とか、司祭とか、しきたり(伝統)とか、ああ、結婚の話が始まったと思いました。
そして、お金の話です。
肉屋のおやじが、牛乳屋の(主役のテヴィエ、市村正親)長女と結婚する話で始まります。肉屋のおやじの妻は死んでいて、再婚です。長女は何も知りません。長女のいないところで、結婚の約束が成立してしまいました。肉屋のおやじは、長女の親であるテヴィエよりも年上です。それでもかまわないのです。なぜなら、肉屋はお金持ちだからです。男にお金があることが大事なのです。されど、長女は当然反発します。
そんな感じで、次女、三女の結婚話が素材になって、すったもんだの争いが起きる劇です。
お金持ち、貧乏、お金か愛情か、ドラマでは、よくある素材です。
安息日(あんそくび):劇中でよく出てきた言葉です。日曜日のことだろうか。調べました。休息・礼拝のための日。テヴィエたちはユダヤ教なので、金曜日の日没から土曜日の日没だそうです。
舞台を観ていて、『タイミングの良さ』に感心しました。
家のセットがあって、人が家の中にある別の部屋に入っていくと、同時に、家の外から別の人が入ってきます。ものすごくきちんとしたタイミングで驚きました。そのほかのことについても、ピシッピシッと動きがきちんと決まっていて、稽古(けいこ)の成果だと感心しました。
演劇のテーマの根底には、『平和』があると感じました。
全体的に、ロシア人に迫害のような対応を受けているユダヤ人の情景があります。
ユダヤ人にとっての、『人間と神の賛歌』がありました。偉大なものを賞賛(しょうさん。ほめたたえる)のです。
舞台は、ときおり、お祭りのようです。歌があって、ダンスがあって、音楽が鳴り響きます。
すごい!と声が何度か出そうになりました。大迫力です。にぎやかで、観ているこちらも楽しい気分になれました。
結婚相手のことで、娘たちから文句を言われて、板挟みになる父親のテヴィエ(市村正親)ですが、がんこそうに見えても、譲る時は譲るという判断をする、いいおやじさんです。
『約束』にこだわる内容でした。
宗教がかなりからんでくるのですが、あまり気にしないようにして観劇しました。
信仰深い人たちの物語です。
若い役者さんたちの歌声に伸びがあって、聴いていて気持ちがいい。
恋愛の成就について応援したくなります。
テヴィエ(市村正親)の動作や言葉にユーモアがあって大笑いできました。
市村正親さんは、最初なんとなくとっつきにくい人かなあと感じましたが、ときおりのしぐさが、志村けんさんみたいで笑いました。おもしろい。76歳の方ですがお元気です。
なんというか、時代背景として、人の気持ちのよりどころが、神しかない時代です。法律とか、思想とか、道徳とか、そういうものはまだぼんやりしていて、宗教で集団が管理されている時代だと受け取りました。宗教で、集団の、『秩序』が保たれているのです。劇中では、『しきたり(伝統)』と表現されていました。
歌劇は大迫力で、ときに、オペラのようだと思いました。(オペラを観たことはありませんが)
最終的には、ユダヤ人たちは、ロシア人たちに住んでいた土地を追い出されてしまいます。
エルサレムへ行く人もいましたが、大半のユダヤ人は、アメリカ合衆国への移住を目指しました。
最後のあたりで交わされた(かわされた)言葉が、『シャローム』という言葉でした。意味は、『平和』です。
最後は尻すぼみするような雰囲気で静かに幕切れとなってしまってあっけなかった。まあ、そういう終わり方もあるのでしょう。以前名古屋伏見にある御園座(みそのざ)で観た、山崎育三郎さんのミュージカル、『トッツィー』もそんな幕切れでした。
流れていた曲で、第1幕の最後に流れた、『陽は昇り又沈む』は聴いたことがある曲です。いい感じの曲です。
オーケストラのみなさんは、舞台の右奥の部屋(あるいはスペース(区域))におられて、ときおり、その場所が見えるように舞台装置が動きました。それもまた、座席から観ていていい感じでした。
観客は、わたしたちのような年金生活者の夫婦が多かった。年配の男女です。
ラストのカーテンコールでは、2000人ぐらいいた観客が総立ちのようになって、大きな拍手が続いて、何度も幕が上がったり下がったりして、出演者のみなさんがたが、せいぞろいでステージの前の方へ出てきて何度も頭を下げておられました。壮観でした。
幕間休憩中(30分間ぐらい)のトイレが大混雑でした。男性客が意外に多く、男性用トイレも行列でしたが、男はそれなりにスムーズに前へ進んでいました。
女性用は、1階のトイレだけではなくて、2階、3階、4階、5階と上のほうが、たぶん利用者が少なくて、穴場のような気がしました。
2025年04月07日
コモドオオトカゲ (名古屋東山動物園にて)
コモドオオトカゲ (名古屋東山動物園にて)
小学校の春休みに、三世代でぞろぞろと動物園へ遊びに行きました。
昨年シンガポール動物園から名古屋に来てくれた、『コモドオオトカゲ』を最初に見ました。
場所は、昔、イケメンゴリラのシャバーニたちがいた旧ゴリラ舎でした。(ゴリラたちは、現在は別の場所にいます)
最初、展示室を観ても、コモドオオトカゲがどこいるのかわかりませんでした。
太い木の幹が何本もころがっています。

トンネルみたいになっている木の幹の下になにか動物の気配がありました。

木の幹だと思っていたのは、コモドオオトカゲ君の本体でした。
カメレオンのようです。周囲の風景と同化しています。身を守るためでしょう。
じーっとながめていたら、こっちを向いてくれました。
もっと厳しい視線をしているのかと予想していましたが、愛らしいつぶらな瞳で、やさしそうな性格に見えました。
でも、口の中に毒をもっているそうです。
全長2m70cm。体重約50kg。お名前は、『タロウ』で、年齢13歳のオスだそうです。
別名が、『コモドドラゴン』で、生息地は、インドネシアの島だそうです。

この日の園内は、桜の花がとてもきれいでした。花びらが輝いていました。
熊太郎じいさんは、長いこと生きてきたので、桜の花は見飽きた気分でしたが、じっさいに今年もそばで見てみると、かなり美しい。あと何回桜の開花を見ることができるだろうかという年齢になってしまいました。
まだちびっこの孫たちとジェットコースターに乗ったり、ボート池でスワン型ボートのペダルをこいだりして春の一日を楽しみました。
小学校の春休みに、三世代でぞろぞろと動物園へ遊びに行きました。
昨年シンガポール動物園から名古屋に来てくれた、『コモドオオトカゲ』を最初に見ました。
場所は、昔、イケメンゴリラのシャバーニたちがいた旧ゴリラ舎でした。(ゴリラたちは、現在は別の場所にいます)
最初、展示室を観ても、コモドオオトカゲがどこいるのかわかりませんでした。
太い木の幹が何本もころがっています。

トンネルみたいになっている木の幹の下になにか動物の気配がありました。

木の幹だと思っていたのは、コモドオオトカゲ君の本体でした。
カメレオンのようです。周囲の風景と同化しています。身を守るためでしょう。
じーっとながめていたら、こっちを向いてくれました。
もっと厳しい視線をしているのかと予想していましたが、愛らしいつぶらな瞳で、やさしそうな性格に見えました。
でも、口の中に毒をもっているそうです。
全長2m70cm。体重約50kg。お名前は、『タロウ』で、年齢13歳のオスだそうです。
別名が、『コモドドラゴン』で、生息地は、インドネシアの島だそうです。

この日の園内は、桜の花がとてもきれいでした。花びらが輝いていました。
熊太郎じいさんは、長いこと生きてきたので、桜の花は見飽きた気分でしたが、じっさいに今年もそばで見てみると、かなり美しい。あと何回桜の開花を見ることができるだろうかという年齢になってしまいました。
まだちびっこの孫たちとジェットコースターに乗ったり、ボート池でスワン型ボートのペダルをこいだりして春の一日を楽しみました。
2024年12月25日
大竹しのぶさん主演『太鼓たたいて、笛吹いて』を観に行く
大竹しのぶさんの音楽劇、『太鼓たたいて、笛吹いて』を観に行く。ウィンクあいちにて(愛知県産業労働センター)
大竹しのぶさんを映像で初めて見たのは、邦画『青春の門』でした。自分は高校生だったと思います。そのときの大竹さんは映画の中では、福岡県の炭鉱町で暮らす娘さんの役でした。
たまたまですが、わたしはそのとき、福岡県の炭鉱町にある映画館で、『青春の門』を見ました。たぶん、大竹さんが出られた最初のシーンは、川があって、大竹しのぶさんは、土手をいっしょうけんめい走っておられました。ロケ地はたぶん、福岡県田川市を流れる中元寺川(ちゅうげんじがわ)だったのではなかろうかと思います。わたしは当時、五木寛之さんが書かれた原作小説をすでに読んでいました。
まだ十代だった大竹しのぶさんを観て、わたしはびっくりしました。こんな清純で、清らかな人がこの世にいるのかと、第一印象で強い衝撃がありました。
その後大竹しのぶさんは、NHKの朝ドラ、『水色の時』に出演されました。舞台は、日本アルプスの山々が見える長野県大町市(おおまちし)だったと思います。高校のときの修学旅行先が黒部立山(くろべたてやま)アルペンルートで、大町市内で宿泊しました。連なる(つらなる)雪をかぶった高い山脈を生まれて初めて見て感激しました。とても美しかった。
2005年に愛知万博があったときに、会場のテントの中から大竹しのぶさんの声が聞こえてきました。あいさつをされて、文部省唱歌のような歌を歌われていました。なにかしらの権利を持った人だけが大竹さんを見ることができるようなエリアになっていました。
2024年ももうすぐ終わりますが、今年1月に、東京ドームそばにあるIMMシアターという劇場で、明石家さんまさんが聖徳太子を演じる喜劇を観劇しました。劇の最後のほうで、さんまさんが舞台から観客席に降りてきて、観客席にある通路をぐるぐる回ってくれたので、さんまさんをそばで見ることができました。そんなこともあって、さんまさんから始まった2024年を、元夫婦の相手であるしのぶさんの舞台劇で締めることにしました。
『太鼓たたいて、笛吹いて』では、大竹しのぶさんが、1935年(昭和10年)ごろからの第二次世界大戦中に向かうという時代に、国民に対して、軍隊のことを鼓舞して(こぶ:士気を高める)、軍隊にとって都合のいいように、国民の意識をコントロールする役割を果たす従軍作家として活動した林芙美子さん(はやしふみこさん。戦前の代表作が、『放浪記』)を演じます。
小説家林芙美子さんは、戦争中に、軍部の加勢をしたという理由で、戦後、世間からの批判にさらされています。
ご本人は、1951年(昭和26年。終戦が昭和20年)に亡くなっています。心臓麻痺で急逝されています。47歳でした。
当時林芙美子さんは、人生の晩年を迎えてうんぬんかんぬんという言葉を残されています。昭和26年当時の日本人の平均寿命が、男性は61歳ぐらい、女性は65歳ぐらいでした。(そのときだったら、わたしはもう死んでいます)
わたしがこどものころは、お年寄りに対して、『長生きしてね』と言ってくれるちびっこがいましたが、今はもうそう言ってくれるこどもさんはいなくなりました。『認知症にならないでね』ですな。
『太鼓たたいて、笛吹いて』は、名古屋駅前にある、『ウィンクあいち(愛知県産業労働センター)』というビルの2階・3階にあるホールで公演されて、夫婦で観に行きました。さんまさんも、しのぶさんもうちら夫婦と同世代なので、思い出がいろいろとよみがえります。
比較的ステージに近い席だったので、大竹しのぶさんの演技をはじめとして、はっきりと観劇することができました。しのぶさんは、林芙美子さんになりきっておられました。憑依(ひょうい)というのでしょうか、のりうつりです。とても長いセリフを暗記されてスラスラとテンポよくおしゃべりされていたので驚嘆しました。(きょうたん:大きな驚きと尊敬)。非常にリズム感がいい演劇でした。ピアノの伴奏に合わせて進行していく音楽劇でもありました。
井上ひさしさんの戯曲作品(ぎきょく:劇の台本)とか、こまつ座のことは、チケットを手に入れたあとで知りました。こまつ座は、井上ひさしさんの作品だけを上演するそうです。
演劇が始まる前に、ふと思い出したことがありました。わたしは二十代のときに内臓の病気で三か月程度入院した経験があるのですが、点滴による入院治療の合間に読んでいた本が、少女漫画の、『ガラスの仮面 美内すずえ(みうち・すずえ) 白泉社(はくせんしゃ)』でした。
とても長い物語で(たぶん今も未完だと思います)何巻も読み続けました。マンガに出てくる主人公の、『北島マヤ』は、大竹しのぶさんのイメージでした。同じく、『姫川亜弓(ひめかわ・あゆみ)』は、大原麗子(おおはら・れいこ)さんのイメージでした。そんなことを思い出しました。


思い出すままに、観劇の感想をここに落としてみます。
影絵からスタートします。出演の皆さんが、影絵の人物になって、スクリーンの向こうにすっくと立っておられます。スクリーンがあがると、人形のような姿かたちをした演者の皆さんが動き出し、おしゃべりを始めます。舞台はセットも演者のお衣装も美しい。
ステージのバックには、緑色の線で描かれた原稿用紙の映像が、ずーっと終わりまで投射され続けます。
『文字』とか、『言葉』にこだわりをもった演劇の内容でした。小説家であること、人間にとって、本がいかにだいじなものであるかがアピール(主張)されていました。
大竹しのぶさんは、大竹しのぶさんではないのじゃないかという印象がずーっと続きました。(林芙美子さんになりきっておられるのです)
3時間ぐらいの公演が終了し、演技が終わって、みなさんがステージにあいさつに出てこられて、観客がスタンディングで(席から立ちあがって)拍手をしたときに、わたしも立ち上がったのですが、大竹しのぶさんのお顔が近くに見えて、演技を終えてほっとされたようすが伝わってきました。大竹さんの体から林芙美子という人物が抜けた瞬間だったのでしょう。
客層は年配の人たちが多かった。あとは、二十代ぐらいに見えるひとりで見に来ている女性がちらほらおられました。お顔がきれいなひとたちなので、女優をめざしておられるのかもしれません。
東京で舞台を観ると、演者と観客が意気投合して、積極的に拍手や笑いが湧きおこり、なかなか楽しくおもしろいのですが、東海地区の劇場だと、観客がなにかしら冷めている(さめている)雰囲気があります。演者が呼びかけても無言です。のりが悪いのです。観慣れていないとか、引いている。お笑いと一緒で、前説(まえせつ):劇場の雰囲気をあらかじめあっためておく役割の人。笑いを誘って、観客の緊張感をほぐしておく人やコンビやグループが必要なのかもしれません。
人間ですから、『お金』の話が出ます。林芙美子さん始めおかあさんも、『お金』が欲しいのです。
『お金』が欲しいから、陸軍の従軍記者のような立場で、小説家の能力を発揮するのです。みなさん、戦争で活躍しましょう。お国のために働きましょう。(でも、命を落とす仕事です。若い命です。演劇を観ていて、今のウクライナとロシアの戦争に行って亡くなる北朝鮮の若い兵士を思い浮かべました)
脇役のみなさんの能力が高い。編集者とか音楽プロデューサーの三木孝を演じられた福井晶一さんという方が、この劇の進行役を果たしていかれます。歌もじょうずです。たいしたものです。
年齢不詳のピアニストの朴勝哲さんもおじょうずでした。ステージの前、まんなかにピアノが設置されていて、朴さんが、客席に背を向けながら、メロディーを奏でます(かなでます)。演者の皆さんが演奏に合わせて何度も歌を歌います。みなさんお歌がおじょうずです。
林芙美子さんという方は、わたしにとっては祖父母の世代の方です。明治生まれです。
むかし、九州の祖父母の家で、中学生だったわたしが祖母と雑談していたときに、東京にいたときに関東大震災を体験したと祖母が言ったのでひっくりかえるほどびっくりしたことがあります。(1923年9月1日(大正12年))。そのときは、もう年寄りになっていた祖母にも、若々しい十代の青春時代があったのだと驚きました。林芙美子さんも関東大震災を体験されています。
大竹しのぶさんが演じる林芙美子さんは、声が甲高い(かんだかい)。元気いっぱいです。そして、『お金』にこだわります。最初からお金持ちであったのではなく、初めは、貧困生活のご苦労があったようです。
でも、小説が売れると、かなりのお金が手元に入ってきた時代だったようです。まわりから寄付金と言う名目でお金をたかられます。
さらに、『戦はもうかる(いくさは、戦争に関係する個人も国(勝利国)も企業ももうかるのです)』、中国南京(なんきん)とか、満州とか、ボルネオ(現在は、州によってマレーシア・ブルネイ・インドネシア各国の領域)の話が出ます。うちの二世代上の親戚にも一家で満州へ渡った家族はいました。また、親の世代の兄弟で、若くして第二次世界大戦中に戦死した人もいました。そんなことも遠い昔のことになりました。現在の日本では、もうずいぶん世代交代が進みました。
日清戦争(1894年(明治27年))、日露戦争(1904年(明治37年))の話題も劇中に出てきました。
『戦(いくさ)はもうかる』という物語をつくって、国民の心理をコントロールして、軍国主義国家を形成して発展させることが軍部の目標です。林芙美子さんの文章作成能力を、そのための道具として活用します。林芙美子さんは、お金と名誉が欲しかった。しかし、途中で気づくのです。自分は間違っていたと。戦後、とても反省されています。
ときおり、『松島』という地名がセリフに出てきます。宮城県の松島海岸のことだろうと思いました。何年か前に訪れたことがあるので、そのときの風景を思い出しながら観劇を楽しみました。
昭和10年代の時代設定ですから、ときおり、政治的にドキッとするような単語がセリフに出てきます。
アカ:共産主義、社会主義を侮辱(ぶじょく。差別)する言葉
アナーキスト:無政府主義者。国家や宗教を否定する。自由人であることを優先する。
セリフにはありませんでしたが、趣旨として、文盲(もんもう)の人:字が読めない人(わたしがこどものころは、お年寄りで、字の読み書きができない人がけっこういました。バスセンターで、行き先や時刻表などの文字が読めなくて困っているお年寄りがいたら助けてあげなさいと先生に教わりました)
非国民(ひこくみん):日本軍や国策を批判する人
『女の幸せは、男にすがること』(男尊女卑の時代です)
『ひとりじゃない』という言葉が繰り返されます。歌も歌われます。
聞いていて、大昔のアイドル歌手、天地真理さん(あまち・まりさん)の歌曲、『ひとりじゃないの』を思い出しました。まだ中学生だったわたしは、天地真理さんのポスターを部屋の壁にはっていました。今思うと、なんか、だまされたような感じです。たしかキャッチフレーズが、『白雪姫』でした。
劇中で、鹿児島市にいたときの話が少し出てきました。
以前鹿児島市の城山公園を訪れたときのことです。桜島から鹿児島湾、鹿児島市の市街地が見渡せる観光地です。
展望台から少し下がったところで、地元の小学生たちが、かけっこのような走る大会をやっていました。先生方や、おもにお母さんのご父兄がたくさんおられて、こどもたちの応援をされていました。 あとで調べたら、城山の登山競走大会というイベントだったようで、作家の向田邦子さんとか林芙美子さんも通ったことがある小学校だったのでびっくりしました。
書道の話が出てきます。島崎こま子という女性が、村役場の看板表示を木の板に書道の筆で書いているシーンなのですが、役場の名称が、『穂波村役場(ほなみむらやくば)』でした。わたしの記憶だと、福岡県内に以前、『嘉穂郡穂波町』という自治体がありました。あれ?と思って調べたら、長野県(現在は山ノ内町)と愛知県(現在は一宮市)、そして、福岡県(現在は飯塚市)に穂波村が過去に実在していました。劇中の設定は、戦時中の疎開先である長野県にあった『穂波村』なのでしょう。
島崎藤村(しまざき・とうそん。小説家。1872年(明治5年)-1943年(昭和18年))の親戚(姪めい)だという、『島崎こま子』を天野はなさんという方が演じておられました。
劇中では重要な人物です。劇中では、藤村が、こま子と関係を持った(近親相姦)というようなぶっそうな話も出ます。まあ、なんというか、演劇はなんでもありですな。避けて通れない人間性を描くことが芸術であり人類の文化なのでしょう。
劇中では、林芙美子さんが養子を迎えたことが紹介されていたのですが、養子さんはその後十代で事故のため亡くなっています。
ずいぶん前のことですが、木曽路にある、『島崎藤村記念館』を訪れたことがあります。岐阜県中津川市にある、『馬籠の宿(まごめのしゅく)』にありました。
藤村は実家で8歳まで暮らしその後、東京へ行き英才教育を受けました。12歳から英語を学び、青年期に詩をつくりはじめ、やがて散文に移行し自費出版で「破戒」を刊行。フランス留学後は英語教師、作文教師、大学でフランス語を教える。
馬籠宿の庄屋の息子として生まれ順風満帆の生涯を送った人だと思っていました。しかし、30代から40代は極貧生活を味わっています。妻やふたりの娘を亡くしています。
50代になってやっと生活が安定し、晩年に『夜明け前』が書かれています。人生の後半では童話が書かれています。
『(第二次世界大戦で日本は)きれいに負けることが必要だ(もう日本の勝ち目はない)』
政府や軍部が、きれいに負ける度胸がなかったから、広島と長崎に原子爆弾が投下された。投下されてやっと敗戦を決心できたという流れで表現がなされます。
反戦劇です。
日本でテレビ放送が始まったのが、1953年(昭和28年)で、林芙美子さんは、1951年(昭和26年)に亡くなっていますから、テレビの時代の人ではありません。劇中では、ラジオ放送がときおり流されます。朗読劇とか、ひとり語りでメッセージを伝えます。
これからの日本を考える世代の試行錯誤が、戦後始まったころのお話でした。
この演劇鑑賞でうちの今年のイベントごとはすべて終了しました。
去年の今頃と比べて、賢く(かしこく)なれたと思います。あわせて、今年もあちこち足を運んで、いい体験を重ねることができました。
サヨナラ2024年、コンニチワ2025年という気分です。あと何年間生きられるかわかりませんが、なるべく明るく楽しい毎日を過ごすことを心がけていきます。
(その後、思いついたこと)
林芙美子さんは、お金を得るために、関係者からそそのかされて、陸軍と同行し、文章を書いて戦況を国民に伝えることで、若き戦闘員の確保、その家族への同調意識をあおったわけですが、ふと考えたのです。そういうことは、戦時中だけではなくて、現在にもあるのではなかろうか。(あおる:仕向ける(しむける)、挑発する(ちょうはつする))
ネットでも週刊誌でも、お金をもらって書いてある文章には、なにかしらの意図がある。(いと:たくらみ、企画、目的。状況に応じての「悪だくみ」)
文章を読んでもらうことによって、お金を出した組織なり個人にとってメリットがある(利益がある)内容で文章が書かれている。ゆえに、つくり話、あるいは、グレーゾーンとして(灰色状態)、じょうずにつくり話に近いことが書いてある。
お金のやりとりがからんだ文章は、正しく、素直に、書き手の本心が文章に織り込まれているわけではない。
書き手が、お金をもらって書いた文章を読むときには、内容が本当に正しいのかと考える注意深さがいる。だまされてはいけない。そう考えたのです。
大竹しのぶさんを映像で初めて見たのは、邦画『青春の門』でした。自分は高校生だったと思います。そのときの大竹さんは映画の中では、福岡県の炭鉱町で暮らす娘さんの役でした。
たまたまですが、わたしはそのとき、福岡県の炭鉱町にある映画館で、『青春の門』を見ました。たぶん、大竹さんが出られた最初のシーンは、川があって、大竹しのぶさんは、土手をいっしょうけんめい走っておられました。ロケ地はたぶん、福岡県田川市を流れる中元寺川(ちゅうげんじがわ)だったのではなかろうかと思います。わたしは当時、五木寛之さんが書かれた原作小説をすでに読んでいました。
まだ十代だった大竹しのぶさんを観て、わたしはびっくりしました。こんな清純で、清らかな人がこの世にいるのかと、第一印象で強い衝撃がありました。
その後大竹しのぶさんは、NHKの朝ドラ、『水色の時』に出演されました。舞台は、日本アルプスの山々が見える長野県大町市(おおまちし)だったと思います。高校のときの修学旅行先が黒部立山(くろべたてやま)アルペンルートで、大町市内で宿泊しました。連なる(つらなる)雪をかぶった高い山脈を生まれて初めて見て感激しました。とても美しかった。
2005年に愛知万博があったときに、会場のテントの中から大竹しのぶさんの声が聞こえてきました。あいさつをされて、文部省唱歌のような歌を歌われていました。なにかしらの権利を持った人だけが大竹さんを見ることができるようなエリアになっていました。
2024年ももうすぐ終わりますが、今年1月に、東京ドームそばにあるIMMシアターという劇場で、明石家さんまさんが聖徳太子を演じる喜劇を観劇しました。劇の最後のほうで、さんまさんが舞台から観客席に降りてきて、観客席にある通路をぐるぐる回ってくれたので、さんまさんをそばで見ることができました。そんなこともあって、さんまさんから始まった2024年を、元夫婦の相手であるしのぶさんの舞台劇で締めることにしました。
『太鼓たたいて、笛吹いて』では、大竹しのぶさんが、1935年(昭和10年)ごろからの第二次世界大戦中に向かうという時代に、国民に対して、軍隊のことを鼓舞して(こぶ:士気を高める)、軍隊にとって都合のいいように、国民の意識をコントロールする役割を果たす従軍作家として活動した林芙美子さん(はやしふみこさん。戦前の代表作が、『放浪記』)を演じます。
小説家林芙美子さんは、戦争中に、軍部の加勢をしたという理由で、戦後、世間からの批判にさらされています。
ご本人は、1951年(昭和26年。終戦が昭和20年)に亡くなっています。心臓麻痺で急逝されています。47歳でした。
当時林芙美子さんは、人生の晩年を迎えてうんぬんかんぬんという言葉を残されています。昭和26年当時の日本人の平均寿命が、男性は61歳ぐらい、女性は65歳ぐらいでした。(そのときだったら、わたしはもう死んでいます)
わたしがこどものころは、お年寄りに対して、『長生きしてね』と言ってくれるちびっこがいましたが、今はもうそう言ってくれるこどもさんはいなくなりました。『認知症にならないでね』ですな。
『太鼓たたいて、笛吹いて』は、名古屋駅前にある、『ウィンクあいち(愛知県産業労働センター)』というビルの2階・3階にあるホールで公演されて、夫婦で観に行きました。さんまさんも、しのぶさんもうちら夫婦と同世代なので、思い出がいろいろとよみがえります。
比較的ステージに近い席だったので、大竹しのぶさんの演技をはじめとして、はっきりと観劇することができました。しのぶさんは、林芙美子さんになりきっておられました。憑依(ひょうい)というのでしょうか、のりうつりです。とても長いセリフを暗記されてスラスラとテンポよくおしゃべりされていたので驚嘆しました。(きょうたん:大きな驚きと尊敬)。非常にリズム感がいい演劇でした。ピアノの伴奏に合わせて進行していく音楽劇でもありました。
井上ひさしさんの戯曲作品(ぎきょく:劇の台本)とか、こまつ座のことは、チケットを手に入れたあとで知りました。こまつ座は、井上ひさしさんの作品だけを上演するそうです。
演劇が始まる前に、ふと思い出したことがありました。わたしは二十代のときに内臓の病気で三か月程度入院した経験があるのですが、点滴による入院治療の合間に読んでいた本が、少女漫画の、『ガラスの仮面 美内すずえ(みうち・すずえ) 白泉社(はくせんしゃ)』でした。
とても長い物語で(たぶん今も未完だと思います)何巻も読み続けました。マンガに出てくる主人公の、『北島マヤ』は、大竹しのぶさんのイメージでした。同じく、『姫川亜弓(ひめかわ・あゆみ)』は、大原麗子(おおはら・れいこ)さんのイメージでした。そんなことを思い出しました。


思い出すままに、観劇の感想をここに落としてみます。
影絵からスタートします。出演の皆さんが、影絵の人物になって、スクリーンの向こうにすっくと立っておられます。スクリーンがあがると、人形のような姿かたちをした演者の皆さんが動き出し、おしゃべりを始めます。舞台はセットも演者のお衣装も美しい。
ステージのバックには、緑色の線で描かれた原稿用紙の映像が、ずーっと終わりまで投射され続けます。
『文字』とか、『言葉』にこだわりをもった演劇の内容でした。小説家であること、人間にとって、本がいかにだいじなものであるかがアピール(主張)されていました。
大竹しのぶさんは、大竹しのぶさんではないのじゃないかという印象がずーっと続きました。(林芙美子さんになりきっておられるのです)
3時間ぐらいの公演が終了し、演技が終わって、みなさんがステージにあいさつに出てこられて、観客がスタンディングで(席から立ちあがって)拍手をしたときに、わたしも立ち上がったのですが、大竹しのぶさんのお顔が近くに見えて、演技を終えてほっとされたようすが伝わってきました。大竹さんの体から林芙美子という人物が抜けた瞬間だったのでしょう。
客層は年配の人たちが多かった。あとは、二十代ぐらいに見えるひとりで見に来ている女性がちらほらおられました。お顔がきれいなひとたちなので、女優をめざしておられるのかもしれません。
東京で舞台を観ると、演者と観客が意気投合して、積極的に拍手や笑いが湧きおこり、なかなか楽しくおもしろいのですが、東海地区の劇場だと、観客がなにかしら冷めている(さめている)雰囲気があります。演者が呼びかけても無言です。のりが悪いのです。観慣れていないとか、引いている。お笑いと一緒で、前説(まえせつ):劇場の雰囲気をあらかじめあっためておく役割の人。笑いを誘って、観客の緊張感をほぐしておく人やコンビやグループが必要なのかもしれません。
人間ですから、『お金』の話が出ます。林芙美子さん始めおかあさんも、『お金』が欲しいのです。
『お金』が欲しいから、陸軍の従軍記者のような立場で、小説家の能力を発揮するのです。みなさん、戦争で活躍しましょう。お国のために働きましょう。(でも、命を落とす仕事です。若い命です。演劇を観ていて、今のウクライナとロシアの戦争に行って亡くなる北朝鮮の若い兵士を思い浮かべました)
脇役のみなさんの能力が高い。編集者とか音楽プロデューサーの三木孝を演じられた福井晶一さんという方が、この劇の進行役を果たしていかれます。歌もじょうずです。たいしたものです。
年齢不詳のピアニストの朴勝哲さんもおじょうずでした。ステージの前、まんなかにピアノが設置されていて、朴さんが、客席に背を向けながら、メロディーを奏でます(かなでます)。演者の皆さんが演奏に合わせて何度も歌を歌います。みなさんお歌がおじょうずです。
林芙美子さんという方は、わたしにとっては祖父母の世代の方です。明治生まれです。
むかし、九州の祖父母の家で、中学生だったわたしが祖母と雑談していたときに、東京にいたときに関東大震災を体験したと祖母が言ったのでひっくりかえるほどびっくりしたことがあります。(1923年9月1日(大正12年))。そのときは、もう年寄りになっていた祖母にも、若々しい十代の青春時代があったのだと驚きました。林芙美子さんも関東大震災を体験されています。
大竹しのぶさんが演じる林芙美子さんは、声が甲高い(かんだかい)。元気いっぱいです。そして、『お金』にこだわります。最初からお金持ちであったのではなく、初めは、貧困生活のご苦労があったようです。
でも、小説が売れると、かなりのお金が手元に入ってきた時代だったようです。まわりから寄付金と言う名目でお金をたかられます。
さらに、『戦はもうかる(いくさは、戦争に関係する個人も国(勝利国)も企業ももうかるのです)』、中国南京(なんきん)とか、満州とか、ボルネオ(現在は、州によってマレーシア・ブルネイ・インドネシア各国の領域)の話が出ます。うちの二世代上の親戚にも一家で満州へ渡った家族はいました。また、親の世代の兄弟で、若くして第二次世界大戦中に戦死した人もいました。そんなことも遠い昔のことになりました。現在の日本では、もうずいぶん世代交代が進みました。
日清戦争(1894年(明治27年))、日露戦争(1904年(明治37年))の話題も劇中に出てきました。
『戦(いくさ)はもうかる』という物語をつくって、国民の心理をコントロールして、軍国主義国家を形成して発展させることが軍部の目標です。林芙美子さんの文章作成能力を、そのための道具として活用します。林芙美子さんは、お金と名誉が欲しかった。しかし、途中で気づくのです。自分は間違っていたと。戦後、とても反省されています。
ときおり、『松島』という地名がセリフに出てきます。宮城県の松島海岸のことだろうと思いました。何年か前に訪れたことがあるので、そのときの風景を思い出しながら観劇を楽しみました。
昭和10年代の時代設定ですから、ときおり、政治的にドキッとするような単語がセリフに出てきます。
アカ:共産主義、社会主義を侮辱(ぶじょく。差別)する言葉
アナーキスト:無政府主義者。国家や宗教を否定する。自由人であることを優先する。
セリフにはありませんでしたが、趣旨として、文盲(もんもう)の人:字が読めない人(わたしがこどものころは、お年寄りで、字の読み書きができない人がけっこういました。バスセンターで、行き先や時刻表などの文字が読めなくて困っているお年寄りがいたら助けてあげなさいと先生に教わりました)
非国民(ひこくみん):日本軍や国策を批判する人
『女の幸せは、男にすがること』(男尊女卑の時代です)
『ひとりじゃない』という言葉が繰り返されます。歌も歌われます。
聞いていて、大昔のアイドル歌手、天地真理さん(あまち・まりさん)の歌曲、『ひとりじゃないの』を思い出しました。まだ中学生だったわたしは、天地真理さんのポスターを部屋の壁にはっていました。今思うと、なんか、だまされたような感じです。たしかキャッチフレーズが、『白雪姫』でした。
劇中で、鹿児島市にいたときの話が少し出てきました。
以前鹿児島市の城山公園を訪れたときのことです。桜島から鹿児島湾、鹿児島市の市街地が見渡せる観光地です。
展望台から少し下がったところで、地元の小学生たちが、かけっこのような走る大会をやっていました。先生方や、おもにお母さんのご父兄がたくさんおられて、こどもたちの応援をされていました。 あとで調べたら、城山の登山競走大会というイベントだったようで、作家の向田邦子さんとか林芙美子さんも通ったことがある小学校だったのでびっくりしました。
書道の話が出てきます。島崎こま子という女性が、村役場の看板表示を木の板に書道の筆で書いているシーンなのですが、役場の名称が、『穂波村役場(ほなみむらやくば)』でした。わたしの記憶だと、福岡県内に以前、『嘉穂郡穂波町』という自治体がありました。あれ?と思って調べたら、長野県(現在は山ノ内町)と愛知県(現在は一宮市)、そして、福岡県(現在は飯塚市)に穂波村が過去に実在していました。劇中の設定は、戦時中の疎開先である長野県にあった『穂波村』なのでしょう。
島崎藤村(しまざき・とうそん。小説家。1872年(明治5年)-1943年(昭和18年))の親戚(姪めい)だという、『島崎こま子』を天野はなさんという方が演じておられました。
劇中では重要な人物です。劇中では、藤村が、こま子と関係を持った(近親相姦)というようなぶっそうな話も出ます。まあ、なんというか、演劇はなんでもありですな。避けて通れない人間性を描くことが芸術であり人類の文化なのでしょう。
劇中では、林芙美子さんが養子を迎えたことが紹介されていたのですが、養子さんはその後十代で事故のため亡くなっています。
ずいぶん前のことですが、木曽路にある、『島崎藤村記念館』を訪れたことがあります。岐阜県中津川市にある、『馬籠の宿(まごめのしゅく)』にありました。
藤村は実家で8歳まで暮らしその後、東京へ行き英才教育を受けました。12歳から英語を学び、青年期に詩をつくりはじめ、やがて散文に移行し自費出版で「破戒」を刊行。フランス留学後は英語教師、作文教師、大学でフランス語を教える。
馬籠宿の庄屋の息子として生まれ順風満帆の生涯を送った人だと思っていました。しかし、30代から40代は極貧生活を味わっています。妻やふたりの娘を亡くしています。
50代になってやっと生活が安定し、晩年に『夜明け前』が書かれています。人生の後半では童話が書かれています。
『(第二次世界大戦で日本は)きれいに負けることが必要だ(もう日本の勝ち目はない)』
政府や軍部が、きれいに負ける度胸がなかったから、広島と長崎に原子爆弾が投下された。投下されてやっと敗戦を決心できたという流れで表現がなされます。
反戦劇です。
日本でテレビ放送が始まったのが、1953年(昭和28年)で、林芙美子さんは、1951年(昭和26年)に亡くなっていますから、テレビの時代の人ではありません。劇中では、ラジオ放送がときおり流されます。朗読劇とか、ひとり語りでメッセージを伝えます。
これからの日本を考える世代の試行錯誤が、戦後始まったころのお話でした。
この演劇鑑賞でうちの今年のイベントごとはすべて終了しました。
去年の今頃と比べて、賢く(かしこく)なれたと思います。あわせて、今年もあちこち足を運んで、いい体験を重ねることができました。
サヨナラ2024年、コンニチワ2025年という気分です。あと何年間生きられるかわかりませんが、なるべく明るく楽しい毎日を過ごすことを心がけていきます。
(その後、思いついたこと)
林芙美子さんは、お金を得るために、関係者からそそのかされて、陸軍と同行し、文章を書いて戦況を国民に伝えることで、若き戦闘員の確保、その家族への同調意識をあおったわけですが、ふと考えたのです。そういうことは、戦時中だけではなくて、現在にもあるのではなかろうか。(あおる:仕向ける(しむける)、挑発する(ちょうはつする))
ネットでも週刊誌でも、お金をもらって書いてある文章には、なにかしらの意図がある。(いと:たくらみ、企画、目的。状況に応じての「悪だくみ」)
文章を読んでもらうことによって、お金を出した組織なり個人にとってメリットがある(利益がある)内容で文章が書かれている。ゆえに、つくり話、あるいは、グレーゾーンとして(灰色状態)、じょうずにつくり話に近いことが書いてある。
お金のやりとりがからんだ文章は、正しく、素直に、書き手の本心が文章に織り込まれているわけではない。
書き手が、お金をもらって書いた文章を読むときには、内容が本当に正しいのかと考える注意深さがいる。だまされてはいけない。そう考えたのです。
2024年08月16日
名古屋東山動植物園 ナイトズー(夜の動物園)
名古屋東山動植物園 ナイトズー(夜の動物園)
前回のナイトズー訪問はたしか2019年(令和元年)でした。
その後コロナ禍もあって、久しぶりの訪問です。
先日知り合いからナイトズーのときに使える招待券を複数もらったので、親族でそろって出かけました。なお、小中学生はもともと無料です。
小学生の孫たちは、動物たちはもう見飽きたのでボートと遊園地だ!と主張しました。
午後4時ごろ入園して、まずは、スワンのペダルボートだ!! と勢いずいていたので、ボート池へ行き、複数のボートに分散して乗って足でペダルをこぎまくりました。ちょっと暑かったけれど、そこそこ楽しめました。
そのあと、遊園地へ移動してから、遊んでいるうちに夕暮れが始まりました。



何回も何回もジェットコースターに乗りました。
コーヒーカップも複数回乗ってぐるぐる目を回しました。
動物園ではありますが、人間さまがいっぱいなので、撮影した写真を必要以上にアップすることはやめておきますが、ほどほどに人出があってにぎやかな雰囲気でした。
『動物園』を訪れたときに、いつも思うのですが、『動物園』には、『平和』があります。
あかちゃん・ちびっこからお年寄りまで、カップルや夫婦、親子、祖父母・孫、お友だち同士など、安心して時間を過ごせる場所と空間があります。
ウクライナやパレスチナガザ地区の人たちにとって、一番必要な安全な場所が、『動物園』にはあります。
前回のナイトズー訪問はたしか2019年(令和元年)でした。
その後コロナ禍もあって、久しぶりの訪問です。
先日知り合いからナイトズーのときに使える招待券を複数もらったので、親族でそろって出かけました。なお、小中学生はもともと無料です。
小学生の孫たちは、動物たちはもう見飽きたのでボートと遊園地だ!と主張しました。
午後4時ごろ入園して、まずは、スワンのペダルボートだ!! と勢いずいていたので、ボート池へ行き、複数のボートに分散して乗って足でペダルをこぎまくりました。ちょっと暑かったけれど、そこそこ楽しめました。
そのあと、遊園地へ移動してから、遊んでいるうちに夕暮れが始まりました。



何回も何回もジェットコースターに乗りました。
コーヒーカップも複数回乗ってぐるぐる目を回しました。
動物園ではありますが、人間さまがいっぱいなので、撮影した写真を必要以上にアップすることはやめておきますが、ほどほどに人出があってにぎやかな雰囲気でした。
『動物園』を訪れたときに、いつも思うのですが、『動物園』には、『平和』があります。
あかちゃん・ちびっこからお年寄りまで、カップルや夫婦、親子、祖父母・孫、お友だち同士など、安心して時間を過ごせる場所と空間があります。
ウクライナやパレスチナガザ地区の人たちにとって、一番必要な安全な場所が、『動物園』にはあります。
2024年08月15日
観劇 ピーターパン 名古屋御園座(みそのざ)
観劇 ピーターパン 名古屋御園座(みそのざ)
自分がまだ小学校低学年のときに、絵本でピーターパンを知りました。
もう半世紀以上前のことです。
今回は小学校低学年の孫たちと観に行きました。
『ピーターパンとは何?』と聞くので、妖精のようなもので、ちびっこたちといっしょに冒険するんだと教えてやりました。ワニに手首を食べられたフック船長のグループとピーターパンのグループが闘う(たたかう)のです。
初代のピーターパン役は、榊原郁恵さんでした。
榊原郁恵さんがデビューされたときに、職場の独身寮で隣の部屋に住んでいたK君に誘われて市民会館へコンサートに行ったことがあります。K君は郁恵さんのファンで、その後も誘われて2回観に行きました。
郁恵さんは、ご主人の渡辺徹さんが2022年(令和4年)ご病気で亡くなってしまいました。
長い時が流れました。
その後、K君とは交流がなくなり、今はどこでどうしているのか、もうわかりません。たしか、岐阜県の山奥の出身でした。

次の写真は、ステージに降りている幕です。
この幕の向こうがステージです。


感想をちょろちょろと落としておきます。
きれいな舞台です。
舞台装置は、色鮮やかで、光は輝き、ピーターパンと三人のこどもたちは、ダイナミックな動きで空中を飛びます。
幻想的でもあります。
冒険の服装を始め、登場人物たちの各種衣装がなかなかいい。
音楽とダンスの世界です。
動きはすばやい。
筋書きはわかりにくい。
観客の感情を誘導して盛り上げようとしているのですが、何かが足りない。
盛り上がりません。
観客の気持ちが引いている。
7月に東京明治座で松平健さんの『暴れん坊将軍劇(あばれんぼうしょうぐんの劇)』とそのあとの歌謡ショーを観たのですが、マツケンサンバでは明治座が揺れるほどの熱狂で盛り上がりました。観客の気持ちがのっていました。観客席のサンバ棒が暗い中、光輝きながら右に左に大きく揺れていました。観客のノリが良かった。
ピーターパンのほうの観客は冷めて(さめて)いました。演者に合わせて歌や手ぶりをしていたのは、観客全体の半数以下でした。なにかしら、気持ちがのりにくい雰囲気がありました。
ピーターパンが観客に向かって、何度も、『信じる?』という呼びかけをするのですが、観客は無言なのです。なにかが足りないのと、観客自身にもどこかしら不思議な雰囲気がありました。神妙に座っていて、おとなしく、みなさんは、何をしにここにきたのだろうかという疑問をわたしはもちました。
舞台構成内容はけっこうにぎやかで充実していたと思います。迫力もありました。それでも、なにか工夫がいるのでしょう。観客のほうもファンならアクション(体の動きや声出し)が必要です。舞台芸術や娯楽の雰囲気は、演じる者と観る者との双方の協力でつくるものです。4割ぐらいの観客が歌とダンスの時には、声を出したり、両手を動かしたりして、アクションやポーズをとっていました。わたしたち夫婦はそうやってエンジョイしていましたが、孫たちはびっくりしたようすで固まっていました。なかなかむずかしいものです。
フック船長も空中を飛ぶとおもしろいのにとふと思いつきました。
コケッコーのニワトリの鳴き声が良かった。
森人(もりびと)たちや、海賊たちの動きも良かった。
基本は対決シーンの連続です。
そして、おとなになりたくない、ずっとこどもでいたいピーターパンです。
劇中のこどもたちは、やがておとなになっていきます。
人間がこどもでいられる期間は案外長くはありません。
そのへんの理屈の表現がむずかしい。
考え込むと、ステージ上が、深刻で暗い雰囲気になってしまいます。
ピーターパンのポイント(けしておとなにはならない)だから変えることもできないのでしょう。
それでもわたしは、観劇に来て良かったと思いました。
楽しい時間でした。
『アッア・アッアアーー』という掛け声が良かった。
何度もみんなで復唱しました。
まだ十代、高校生のころ、こういうことをする仕事につきたいと思っていましたが、生活していくためにあきらめました。
しかたがありません。それで良かったと思っています。
三幕あって、幕間休憩が各15分間の2回、全体で2時間40分ぐらいの公演でした。
男子トイレはスムーズに利用できました。
女子トイレは、行列は長いけれど、個室がたくさんあるので、トイレに入ってからはスムーズに利用できたそうです。だから、あせる必要はないそうです。
なお食事は座席でできます。
自分がまだ小学校低学年のときに、絵本でピーターパンを知りました。
もう半世紀以上前のことです。
今回は小学校低学年の孫たちと観に行きました。
『ピーターパンとは何?』と聞くので、妖精のようなもので、ちびっこたちといっしょに冒険するんだと教えてやりました。ワニに手首を食べられたフック船長のグループとピーターパンのグループが闘う(たたかう)のです。
初代のピーターパン役は、榊原郁恵さんでした。
榊原郁恵さんがデビューされたときに、職場の独身寮で隣の部屋に住んでいたK君に誘われて市民会館へコンサートに行ったことがあります。K君は郁恵さんのファンで、その後も誘われて2回観に行きました。
郁恵さんは、ご主人の渡辺徹さんが2022年(令和4年)ご病気で亡くなってしまいました。
長い時が流れました。
その後、K君とは交流がなくなり、今はどこでどうしているのか、もうわかりません。たしか、岐阜県の山奥の出身でした。

次の写真は、ステージに降りている幕です。
この幕の向こうがステージです。


感想をちょろちょろと落としておきます。
きれいな舞台です。
舞台装置は、色鮮やかで、光は輝き、ピーターパンと三人のこどもたちは、ダイナミックな動きで空中を飛びます。
幻想的でもあります。
冒険の服装を始め、登場人物たちの各種衣装がなかなかいい。
音楽とダンスの世界です。
動きはすばやい。
筋書きはわかりにくい。
観客の感情を誘導して盛り上げようとしているのですが、何かが足りない。
盛り上がりません。
観客の気持ちが引いている。
7月に東京明治座で松平健さんの『暴れん坊将軍劇(あばれんぼうしょうぐんの劇)』とそのあとの歌謡ショーを観たのですが、マツケンサンバでは明治座が揺れるほどの熱狂で盛り上がりました。観客の気持ちがのっていました。観客席のサンバ棒が暗い中、光輝きながら右に左に大きく揺れていました。観客のノリが良かった。
ピーターパンのほうの観客は冷めて(さめて)いました。演者に合わせて歌や手ぶりをしていたのは、観客全体の半数以下でした。なにかしら、気持ちがのりにくい雰囲気がありました。
ピーターパンが観客に向かって、何度も、『信じる?』という呼びかけをするのですが、観客は無言なのです。なにかが足りないのと、観客自身にもどこかしら不思議な雰囲気がありました。神妙に座っていて、おとなしく、みなさんは、何をしにここにきたのだろうかという疑問をわたしはもちました。
舞台構成内容はけっこうにぎやかで充実していたと思います。迫力もありました。それでも、なにか工夫がいるのでしょう。観客のほうもファンならアクション(体の動きや声出し)が必要です。舞台芸術や娯楽の雰囲気は、演じる者と観る者との双方の協力でつくるものです。4割ぐらいの観客が歌とダンスの時には、声を出したり、両手を動かしたりして、アクションやポーズをとっていました。わたしたち夫婦はそうやってエンジョイしていましたが、孫たちはびっくりしたようすで固まっていました。なかなかむずかしいものです。
フック船長も空中を飛ぶとおもしろいのにとふと思いつきました。
コケッコーのニワトリの鳴き声が良かった。
森人(もりびと)たちや、海賊たちの動きも良かった。
基本は対決シーンの連続です。
そして、おとなになりたくない、ずっとこどもでいたいピーターパンです。
劇中のこどもたちは、やがておとなになっていきます。
人間がこどもでいられる期間は案外長くはありません。
そのへんの理屈の表現がむずかしい。
考え込むと、ステージ上が、深刻で暗い雰囲気になってしまいます。
ピーターパンのポイント(けしておとなにはならない)だから変えることもできないのでしょう。
それでもわたしは、観劇に来て良かったと思いました。
楽しい時間でした。
『アッア・アッアアーー』という掛け声が良かった。
何度もみんなで復唱しました。
まだ十代、高校生のころ、こういうことをする仕事につきたいと思っていましたが、生活していくためにあきらめました。
しかたがありません。それで良かったと思っています。
三幕あって、幕間休憩が各15分間の2回、全体で2時間40分ぐらいの公演でした。
男子トイレはスムーズに利用できました。
女子トイレは、行列は長いけれど、個室がたくさんあるので、トイレに入ってからはスムーズに利用できたそうです。だから、あせる必要はないそうです。
なお食事は座席でできます。
2024年03月01日
観劇 名古屋御園座 ミュージカル『トッツィー』
観劇 名古屋御園座(みそのざ) ミュージカル『トッツィー』
山崎育三郎さんの舞台です。
映画は観たことがあります。もうずいぶん前の洋画です。1983年(昭和58年)日本公開、ダスティン・ホフマンさんの映画でした。
山崎育三郎さんは、出川哲朗さんの充電バイクの番組に出演されたのを見て、好青年で感じのいい人だと思いました。ファンになりました。
NHKの朝ドラでの甲子園高校野球の歌がとても良かった。強い印象で記憶に残っています。
毎週日曜日の夜にある井桁弘恵さん(いげた・ひろえ)さんとゲストを迎えてのトークショー、『おしゃれクリップ』も楽しみに観ています。
女ばかりの観客のところに、男一人で観に行くのはつらいので、奥さんに同行してもらいました。
御園座(みそのざ)はまだ建て替える前、三十年ちょっと前に行ったのが最後です。
まだ、今の年齢の自分よりも若かった五十代の実母とふたりで、『西郷輝彦ショー』を観ました。
親戚からもらった招待券で、2階だったか、3階だったか、座席の上の方、遠い位置から舞台を見下ろした記憶が残っています。『星のフラメンコ』の歌を聴いたことを覚えています。もう、遠い昔のことになりました。
さて、今回のトッツィーは、売れない男優が女装をして女優になったら売れたというコメディです。内容のおもしろさと山崎育三郎さんの魅力で観たいと思いました。
演劇終了後、緞帳(どんちょう。幕(まく))とタイトル照明の撮影はOKだったので撮ってみました。次の写真です。
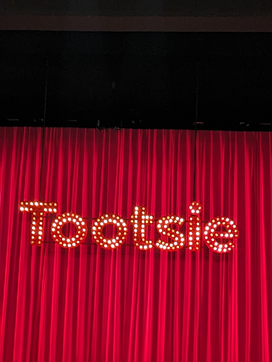


始まる前に、ロビーのイスに座って、はらごしらえのパンを食べていました。(午後4時15分開場、午後5時開演、幕間休憩30分で、終わりは午後8時過ぎだった記憶です。幕間休憩30分間のときに、座席でお弁当を食べている人たちもいて、席で食事はOKでした)
ロビーの壁にかかっていた、たくさんのちょうちんがきれいでした。パンを食べながらちょうちんをながめていました。

ちょうちんを見上げながら、株式投資のことを思い出しました。
ちょうちんに書かれているUFJ銀行も三菱商事も株価が上昇しました。何度か売り買いをしている銘柄です。
思うに、ここにちょうちんがある会社や組織は、御園座が建て替えになる時に、建設費用としていくらかの寄付をされたのでしょう。そのみかえりとして、会社等の宣伝用にちょうちんを出してもらっているのでしょう。ひとつのちょうちんを出す経費がいくらだったのかは、想像するしかありません。

ロビーで、カーテンコール(公演終了後、観客の拍手に応じて幕を開ける)のときのダンスが紹介されていました。ミュージカルの最後に、観客みんなで軽い踊りをするのかと思ったら、なにもありませんでした。
東京で、森公美子さんの『天使にラブ・ソングを』を観たときは、男優さんがステージのふちっこ、ちょっと前に出てきて、観客を誘導しながら上半身だけの軽いダンスを楽しみました。ステージには、出演されたみなさんが並んでいて、いっしょに動作をしてほのぼのとしました。
今回のカーテンコールでは、何度も幕が上がったり下がったりして、演者のみなさんたちが観客に笑顔をふりまいておられました。わたしとしては、それで十分でした。
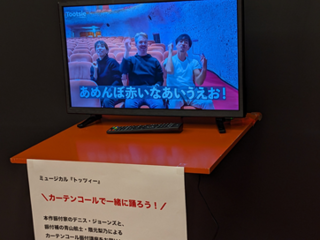
新しい御園座の上の方は、分譲マンション・賃貸マンションになっています。
東京都内のマンション価格との比較で、東京に住む人たちからみれば、名古屋のマンション分譲価格は賃貸月額も含めて、安価だと感じると思います。

さて、思い出すままに、劇の感想を書き落としてみます。
演者のみなさんは若い。若々しくて、元気いっぱいです。ダンスのキレもよく、観ていて気持ちがいい。勢いがあります。
山崎育三郎さんは、男っぽい。テレビで見るのとは違います。テレビだと、細くてきゃしゃな色男的弱さ(色男、金と力はなかりけり)があるのですが、実物はぜんぜん違っていました。ごつくて、力強くて、たくましい男のにおいがプンプン広がってくるような男性でした。(この劇では、女装して女優を演じられていましたが、その姿もピシッと決まっていて、なかなか見事な女優さんを演じておられました。声も女性の声として、高い声を出しておられました。体の大きな女の人です。男から女、女から男への衣装の早変わりがすばやいことに驚きました。演劇は、女性賛歌のステージでした)
山崎育三郎さんは、歌がうまい。声量があって、とくに、声の伸びがいい。
劇の始まりでは、40歳になっても、売れない男優で、役をもらえないと嘆いているところからはじまりますが、それを見ていて、自分も十代のころは、こういう文化芸術・芸能の仕事をしてみたかったけれど、それでは食べていけないわけで、現実は厳しいと割り切って、地味な仕事をコツコツと定年まで続けてきたことを思いだしました。リタイヤして、ようやく、自分のやりたいことができる時間を手に入れたので、これからは、演劇や芸能への参加はできないけれど、観る立場で演者のみなさんを応援していきたいと思ったのです。
劇中では、売れない男優が女装して女優を演じて、オーディションに合格して、劇に出演して大人気が出るのです。でも、男だからウソなのです。だからトラブルが起きるのです。恋愛模様でトラブルになります。三角関係があるのですが、女の立場で、同性同士のラブも生まれます。ややこしい。
ロミオとジュリエットが題材として扱われます。
なんというか、筋書きはあまり肝心なものではありません。
ミュージカルですから、歌とダンスでお客さんに楽しんでもらう内容です。
そして、笑いがあります。コメディです。
男の笑いのツボと女の笑いのツボは違うと感じました。
けっこう、女性のお客さんたちが大きな声をだして笑っておられました。男の自分はどうして笑えるのか不思議でした。笑いのツボが違うのです。
下ネタも多い。案外、女性のお客さんって、下ネタが好きなんだと驚きました。まあ、エロっぽい話もあります。キスシーンを何度も観ました。まあ、あいさつのようなものなのでしょう。
劇が始まる前に、ロビーをゆきかう女性客のみなさんを目にしたのですが、みなさん、めいっぱいおしゃれをされてきておられます。お洋服と靴とバッグと装飾品と、この機会を楽しみにされていることがわかりました。
年配の女性も多い。係員の介助が必要な方もおられました。楽しみにされているのだと思います。
自分も歳をとってわかったのですが、寿命という時間をだいじにしたい。限りがある残りの自分の持ち時間を十分楽しんであの世に旅立ちたいのです。歳をとると、お金よりも『時間』のほうが、愛おしく(いとおしく)思えるようになるのです。
ステージ上の舞台装置は、色も照明も鮮やかできれいに輝いていました。
あとさきのことになりますが、ステージ開始時に、まず、指揮者が、ステージ前のオーケストラピットから姿を現し(あらわし)ます。指揮者は、万歳のように両手をあげて、手拍子(てびょうし)をとり、観客に手拍子をするようにうながします。観客全員の手拍子の音はだんだん大きく速く(はやく)なってきて、雰囲気が盛り上がります。指揮者は、楽団だけではなくて、観客も指揮するのです。なかなかいい感じです。
展開として、山崎育三郎さんが演じている女優が、男であることがばれます。
その瞬間、舞台上は、暗い雰囲気になります。
山崎育三郎さんの熟女女優に心を奪われる若い男優がいるのですが、あんな男が実際にいるのかなあと思いながら観ていました。いないと思います。まあ、劇です。
山崎育三郎さんが、演技ですが、ウォッカだったかを瓶から(びんから)ラッパ飲みするシーンが何度も出てきました。セリフを言う時に呼吸がしにくいだろうにと思いました。
エージェント:契約交渉の代理人
デコルテ:胸元から肩・首まわり。その部分が開いたドレス。
ジェンダー:つくられた男性像、女性像。社会的性別
山崎育三郎さんの良かったセリフとして:『(わたしのことを)女王さまとお呼びーー』
男であることがばれて、乱れた男女関係や人間関係のトラブルについて、いろいろ修復に走って、最後は、男女の和解シーンで終わりますが、最後はあっけなかった。しんみりとして、突然幕が下り(おり)ました。
えッ?! 終わり? 尻切れトンボ感がありましたが、その後、何回ものカーテンコールで、幕があがったりさがったりしたので、まあいいかでした。
ミュージカルの最後というものは、出演者全員がステージに出てきて、踊って歌ってパーーとやるものだと思いこんでいました。ハッピーエンドパターンです。
楽しませてもらいました。
演者のみなさん、ありがとう。
山崎育三郎さんの舞台です。
映画は観たことがあります。もうずいぶん前の洋画です。1983年(昭和58年)日本公開、ダスティン・ホフマンさんの映画でした。
山崎育三郎さんは、出川哲朗さんの充電バイクの番組に出演されたのを見て、好青年で感じのいい人だと思いました。ファンになりました。
NHKの朝ドラでの甲子園高校野球の歌がとても良かった。強い印象で記憶に残っています。
毎週日曜日の夜にある井桁弘恵さん(いげた・ひろえ)さんとゲストを迎えてのトークショー、『おしゃれクリップ』も楽しみに観ています。
女ばかりの観客のところに、男一人で観に行くのはつらいので、奥さんに同行してもらいました。
御園座(みそのざ)はまだ建て替える前、三十年ちょっと前に行ったのが最後です。
まだ、今の年齢の自分よりも若かった五十代の実母とふたりで、『西郷輝彦ショー』を観ました。
親戚からもらった招待券で、2階だったか、3階だったか、座席の上の方、遠い位置から舞台を見下ろした記憶が残っています。『星のフラメンコ』の歌を聴いたことを覚えています。もう、遠い昔のことになりました。
さて、今回のトッツィーは、売れない男優が女装をして女優になったら売れたというコメディです。内容のおもしろさと山崎育三郎さんの魅力で観たいと思いました。
演劇終了後、緞帳(どんちょう。幕(まく))とタイトル照明の撮影はOKだったので撮ってみました。次の写真です。
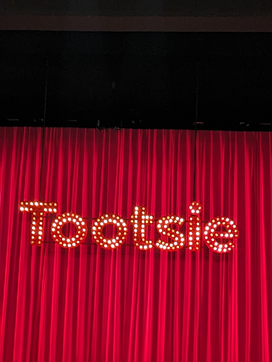


始まる前に、ロビーのイスに座って、はらごしらえのパンを食べていました。(午後4時15分開場、午後5時開演、幕間休憩30分で、終わりは午後8時過ぎだった記憶です。幕間休憩30分間のときに、座席でお弁当を食べている人たちもいて、席で食事はOKでした)
ロビーの壁にかかっていた、たくさんのちょうちんがきれいでした。パンを食べながらちょうちんをながめていました。

ちょうちんを見上げながら、株式投資のことを思い出しました。
ちょうちんに書かれているUFJ銀行も三菱商事も株価が上昇しました。何度か売り買いをしている銘柄です。
思うに、ここにちょうちんがある会社や組織は、御園座が建て替えになる時に、建設費用としていくらかの寄付をされたのでしょう。そのみかえりとして、会社等の宣伝用にちょうちんを出してもらっているのでしょう。ひとつのちょうちんを出す経費がいくらだったのかは、想像するしかありません。

ロビーで、カーテンコール(公演終了後、観客の拍手に応じて幕を開ける)のときのダンスが紹介されていました。ミュージカルの最後に、観客みんなで軽い踊りをするのかと思ったら、なにもありませんでした。
東京で、森公美子さんの『天使にラブ・ソングを』を観たときは、男優さんがステージのふちっこ、ちょっと前に出てきて、観客を誘導しながら上半身だけの軽いダンスを楽しみました。ステージには、出演されたみなさんが並んでいて、いっしょに動作をしてほのぼのとしました。
今回のカーテンコールでは、何度も幕が上がったり下がったりして、演者のみなさんたちが観客に笑顔をふりまいておられました。わたしとしては、それで十分でした。
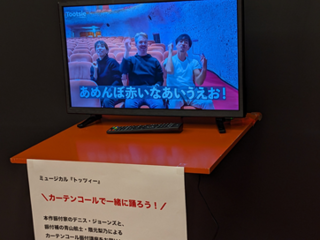
新しい御園座の上の方は、分譲マンション・賃貸マンションになっています。
東京都内のマンション価格との比較で、東京に住む人たちからみれば、名古屋のマンション分譲価格は賃貸月額も含めて、安価だと感じると思います。

さて、思い出すままに、劇の感想を書き落としてみます。
演者のみなさんは若い。若々しくて、元気いっぱいです。ダンスのキレもよく、観ていて気持ちがいい。勢いがあります。
山崎育三郎さんは、男っぽい。テレビで見るのとは違います。テレビだと、細くてきゃしゃな色男的弱さ(色男、金と力はなかりけり)があるのですが、実物はぜんぜん違っていました。ごつくて、力強くて、たくましい男のにおいがプンプン広がってくるような男性でした。(この劇では、女装して女優を演じられていましたが、その姿もピシッと決まっていて、なかなか見事な女優さんを演じておられました。声も女性の声として、高い声を出しておられました。体の大きな女の人です。男から女、女から男への衣装の早変わりがすばやいことに驚きました。演劇は、女性賛歌のステージでした)
山崎育三郎さんは、歌がうまい。声量があって、とくに、声の伸びがいい。
劇の始まりでは、40歳になっても、売れない男優で、役をもらえないと嘆いているところからはじまりますが、それを見ていて、自分も十代のころは、こういう文化芸術・芸能の仕事をしてみたかったけれど、それでは食べていけないわけで、現実は厳しいと割り切って、地味な仕事をコツコツと定年まで続けてきたことを思いだしました。リタイヤして、ようやく、自分のやりたいことができる時間を手に入れたので、これからは、演劇や芸能への参加はできないけれど、観る立場で演者のみなさんを応援していきたいと思ったのです。
劇中では、売れない男優が女装して女優を演じて、オーディションに合格して、劇に出演して大人気が出るのです。でも、男だからウソなのです。だからトラブルが起きるのです。恋愛模様でトラブルになります。三角関係があるのですが、女の立場で、同性同士のラブも生まれます。ややこしい。
ロミオとジュリエットが題材として扱われます。
なんというか、筋書きはあまり肝心なものではありません。
ミュージカルですから、歌とダンスでお客さんに楽しんでもらう内容です。
そして、笑いがあります。コメディです。
男の笑いのツボと女の笑いのツボは違うと感じました。
けっこう、女性のお客さんたちが大きな声をだして笑っておられました。男の自分はどうして笑えるのか不思議でした。笑いのツボが違うのです。
下ネタも多い。案外、女性のお客さんって、下ネタが好きなんだと驚きました。まあ、エロっぽい話もあります。キスシーンを何度も観ました。まあ、あいさつのようなものなのでしょう。
劇が始まる前に、ロビーをゆきかう女性客のみなさんを目にしたのですが、みなさん、めいっぱいおしゃれをされてきておられます。お洋服と靴とバッグと装飾品と、この機会を楽しみにされていることがわかりました。
年配の女性も多い。係員の介助が必要な方もおられました。楽しみにされているのだと思います。
自分も歳をとってわかったのですが、寿命という時間をだいじにしたい。限りがある残りの自分の持ち時間を十分楽しんであの世に旅立ちたいのです。歳をとると、お金よりも『時間』のほうが、愛おしく(いとおしく)思えるようになるのです。
ステージ上の舞台装置は、色も照明も鮮やかできれいに輝いていました。
あとさきのことになりますが、ステージ開始時に、まず、指揮者が、ステージ前のオーケストラピットから姿を現し(あらわし)ます。指揮者は、万歳のように両手をあげて、手拍子(てびょうし)をとり、観客に手拍子をするようにうながします。観客全員の手拍子の音はだんだん大きく速く(はやく)なってきて、雰囲気が盛り上がります。指揮者は、楽団だけではなくて、観客も指揮するのです。なかなかいい感じです。
展開として、山崎育三郎さんが演じている女優が、男であることがばれます。
その瞬間、舞台上は、暗い雰囲気になります。
山崎育三郎さんの熟女女優に心を奪われる若い男優がいるのですが、あんな男が実際にいるのかなあと思いながら観ていました。いないと思います。まあ、劇です。
山崎育三郎さんが、演技ですが、ウォッカだったかを瓶から(びんから)ラッパ飲みするシーンが何度も出てきました。セリフを言う時に呼吸がしにくいだろうにと思いました。
エージェント:契約交渉の代理人
デコルテ:胸元から肩・首まわり。その部分が開いたドレス。
ジェンダー:つくられた男性像、女性像。社会的性別
山崎育三郎さんの良かったセリフとして:『(わたしのことを)女王さまとお呼びーー』
男であることがばれて、乱れた男女関係や人間関係のトラブルについて、いろいろ修復に走って、最後は、男女の和解シーンで終わりますが、最後はあっけなかった。しんみりとして、突然幕が下り(おり)ました。
えッ?! 終わり? 尻切れトンボ感がありましたが、その後、何回ものカーテンコールで、幕があがったりさがったりしたので、まあいいかでした。
ミュージカルの最後というものは、出演者全員がステージに出てきて、踊って歌ってパーーとやるものだと思いこんでいました。ハッピーエンドパターンです。
楽しませてもらいました。
演者のみなさん、ありがとう。



